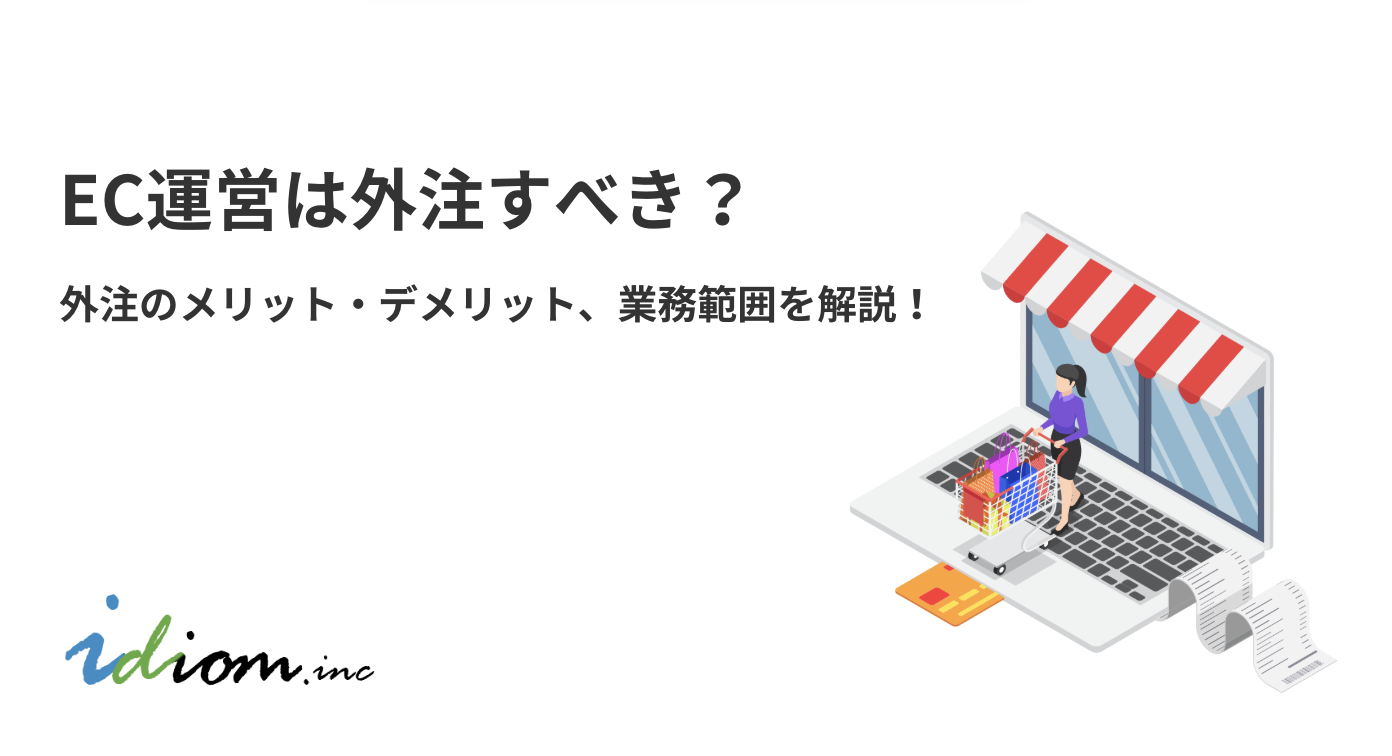ECサイトの運営には、商品登録、在庫管理、広告運用、カスタマーサポートなど多くの作業が発生します。
事業の立ち上げ当初は自社内で対応できても、売上が伸びるにつれて業務量が増え、社内で回しきれず、運用の質が落ちてきたと感じるケースも少なくありません。こうした悩みからEC運営を外注すべきかという検討が生まれます。
しかし、外注にはコストやコミュニケーション面の課題もあるため、安易に決めるのはリスクです。この記事では、EC運営を内製するメリット・デメリット、外注する際の判断基準、よくある失敗とその回避策までを網羅的に解説します。最適な運営体制を見つけたい方は、ぜひ参考にしてください。
 idiomは、10年以上にわたってECビジネスを支援し、これまでに100社以上との取引実績を持っています。
idiomは、10年以上にわたってECビジネスを支援し、これまでに100社以上との取引実績を持っています。
立ち上げから運用改善までを一貫して伴走し、多くの企業の成長を後押ししてきました。
さらに、運営継続率は95%と非常に高く、成果と信頼の両面で実績があります。
初期費用を抑えられる成果報酬型のプランもご用意しており、ECをこれから始めたい企業様でも安心してスタートいただけます。
▼▼▼まずはお気軽にご相談ください。▼▼▼
ECサイト運営代行のご相談はidiomへ
EC運用を外注する3つのメリット
ECサイトの運営は、多くの業務と専門知識を要するため、社内リソースだけでは対応が難しくなることもあります。
特に売上拡大フェーズでは、業務の煩雑化やスピード感の低下が課題となります。
そんなときに検討すべきが「EC運用の外注」です。ここでは、外注化によって得られる3つの主なメリットを解説します。
▼EC運用を外注する3つのメリット
|
メリット①|業務の効率化とリソース最適化
EC運営には商品登録、受発注管理、顧客対応、広告運用など多岐にわたる作業が発生します。
これらをすべて内製で行うと、人的リソースが分散し、コア業務に集中できなくなるリスクがあります。
外注によってこれらの業務をプロに任せることで、社内の工数を削減し、マーケティングや商品開発といった本来注力すべき領域に集中できます。
結果として業務全体の効率が向上し、経営資源の最適化が実現します。
メリット②|専門的な知見・ノウハウを活用できる
EC運営代行業者は、多くのクライアント支援で蓄積した豊富な知見と実績を有しています。
たとえば、広告運用におけるA/Bテストのノウハウや、CVR改善に向けたUI/UXの最適化など、自社では得られにくい情報を元に施策を展開可能です。
常に最新のアルゴリズムや市場動向をキャッチアップしているため、自社内では難しい専門的な対応や施策立案をスピーディに実施できる点も大きな魅力です。
メリット③|スピード感のある改善・PDCAが可能
外注先の多くは、複数のプロジェクトを並行して回しているため、PDCAを高速で回す体制が整っています。
データ分析に基づく改善提案や、施策実行までのスピード感は、社内運用ではなかなか再現できません。
また、客観的な第三者視点でのフィードバックも得られるため、改善の精度が上がり、ECサイト全体の成果に直結しやすくなります。
とくに競争の激しいジャンルでは、このスピードが成否を分ける要因となります。
EC運用を外注する3つのデメリット
 ECサイト運営の外注には多くのメリットがある一方で、注意しなければならないデメリットも存在します。
ECサイト運営の外注には多くのメリットがある一方で、注意しなければならないデメリットも存在します。
外部パートナーとの連携や、コスト・ノウハウの蓄積といった点で、思わぬ落とし穴にはまる可能性もあります。
ここでは、EC運用を外注する際に押さえておくべき3つの代表的なデメリットを解説します。
▼EC運用を外注する3つのデメリット
|
デメリット①|コストがかかる
外注の最大のデメリットは、やはりコスト面です。
業務内容によっては月数十万円〜百万円単位の費用が発生することもあり、特に売上が安定していない立ち上げ期や中小規模のEC事業者にとっては大きな負担になります。
また、安価な業者を選ぶと品質や対応スピードに難がある場合もあり、結果的に成果が出ずコスト倒れになるリスクも。
費用対効果を見極めながら、必要な業務だけを絞って委託するなどの工夫が求められます。
デメリット②|意図が伝わりにくい・連携に時間がかかる
外注先とは別企業である以上、自社のビジョンや細かなニュアンスが伝わりにくいという課題は避けられません。
特にブランドイメージや顧客体験にこだわる企業にとっては、表現のずれや対応方針の相違がトラブルの火種になります。
また、日々の業務連絡や修正依頼に時間がかかることで、スピード感に欠ける運用になってしまうこともあります。
スムーズな連携を図るためには、情報共有のフローや担当窓口の明確化が欠かせません。
デメリット③|ノウハウが社内に蓄積されない
EC運用をすべて外注に任せてしまうと、社内にノウハウが残らず、担当者が育たないという問題も生じます。
短期的には効率的に見えても、いざ内製化やベンダー変更が必要になった際に、スムーズな引き継ぎができず、運用に支障をきたす恐れがあります。
中長期的に自社運用の体制を築くことを視野に入れるなら、段階的なノウハウの共有や、並行して社内人材の育成を進める戦略が必要です。
ECサイトを内製するメリット
ECサイトの運営体制を考える際、「外注か内製か」は重要な判断ポイントです。
特に立ち上げ期や少人数体制の企業では、内製での運用に多くの利点があります。
ここでは、ECサイトを自社で運営することで得られる3つの大きなメリットについて、実務視点で詳しく解説します。
▼ECサイトを内製するメリット
|
メリット①|運用の自由度・スピードが高い
内製化の最大の強みは、意思決定から実行までのスピード感です。
バナーの差し替え、キャンペーンの企画、商品ページの更新といった細かい作業も、自社で完結できるため即時対応が可能になります。
外注では契約範囲や連絡フローがボトルネックになることも多く、「思いついたときにすぐ動ける」体制は、変化の激しいEC市場において大きな武器となります。特に小回りの利く運営が求められる成長期には有利です。
メリット②|自社ノウハウが蓄積される
内製での運用を続けることで、EC業務に関する知見が社内に蓄積され、担当者のスキルアップにもつながります。
たとえば、顧客対応の傾向分析から商品改善のヒントを得たり、広告運用の効果検証をもとに訴求ポイントを磨いたりと、あらゆるデータと学びが企業の資産になります。
これは将来的に体制拡大や新規事業展開を行う際にも、スムーズにノウハウを展開できる基盤となるでしょう。
メリット③|コストを抑えられる場合がある
一見、外注のほうが効率的に見えるかもしれませんが、社内リソースを活用できる場合、内製のほうがコストを抑えられるケースもあります。
特に、Web制作・ライティング・広告運用など一部のスキルが社内にある企業では、初期費用や運用コストを大幅にカット可能です。
また、費用対効果の視点からも「売上がまだ小さい段階では内製」「一定規模を超えたら部分外注」といった段階的な戦略を組みやすいのもメリットの一つです。
ECサイトを内製するデメリット
ECサイトを内製で運用することは、自由度やコスト面でのメリットがある一方で、いくつかの重要な課題も伴います。
とくに人的リソースや知識面での限界は、運営効率や成長性に直結します。ここでは、内製運用における3つの代表的なデメリットを具体的に解説します。
▼ECサイトを内製するデメリット
|
デメリット①|人手不足・属人化しやすい
内製運用では、商品登録から広告運用、顧客対応まで多岐にわたる業務を限られたスタッフでこなす必要があるため、慢性的な人手不足に陥りやすくなります。
また、特定の担当者に業務が集中することで属人化が進み、退職や長期休暇が運用全体のリスク要因となります。
業務の標準化やマニュアル整備が追いつかず、ブラックボックス化することで、結果的にチーム全体の生産性や柔軟性が損なわれるケースも多いです。
デメリット②|成長スピードに限界がある
内製による運用は、スピード感のある立ち上げが可能な反面、売上拡大フェーズではその体制が足かせになることもあります。
広告運用やデータ分析など、専門的かつ継続的な最適化が求められる領域では、リソース不足により改善のスピードが鈍化しやすいです。
また、外注であれば短期間で成果が期待できる施策も、社内の経験値や工数の限界により実行が遅れ、ビジネスチャンスを逃す要因にもなります。
デメリット③|最新のトレンド・技術に対応しづらい
EC市場は日々進化しており、AI活用によるレコメンド強化や動画活用、SNS連動など、最新トレンドやツールの活用が売上に大きく影響します。
しかし、内製体制ではこうした最新技術に関する情報のキャッチアップや導入に時間がかかり、競合に後れを取るリスクがあります。
社内に専門知識を持つ人材がいない場合、技術的なボトルネックが長期間放置されるケースも多く、成長の天井が早期に訪れる可能性も否めません。
idiomは、10年以上にわたってECビジネスを支援し、これまでに100社以上との取引実績を持っています。
立ち上げから運用改善までを一貫して伴走し、多くの企業の成長を後押ししてきました。
さらに、運営継続率は95%と非常に高く、成果と信頼の両面で実績があります。
初期費用を抑えられる成果報酬型のプランもご用意しており、ECをこれから始めたい企業様でも安心してスタートいただけます。
▼▼▼まずはお気軽にご相談ください。▼▼▼
ECサイト運営代行のご相談はidiomへ
EC運営の業務範囲はどこまで外注できる?
ECサイトの運営には多岐にわたる業務が存在し、社内リソースだけで全てを対応するのは現実的ではありません。
そこで注目されるのが「運営業務の外注」です。
しかし、外注可能な範囲は業者ごとに異なり、どこまで任せるべきか判断に迷うこともあります。
本項では、EC運営で外注できる代表的な業務範囲を5つに分けて具体的に解説します。
▼EC運営の業務範囲はどこまで外注できる?
|
①商品登録・在庫管理
商品登録や在庫管理といったバックエンド業務は、比較的外注しやすい領域です。
たとえば商品名、説明文、画像のアップロード、SKU登録などの作業はマニュアル化しやすく、外部の事務代行会社やEC運営代行業者に依頼することで、社内の工数を大幅に削減できます。
また、在庫数の調整や入出荷のデータ入力なども定型業務であるため、システム連携が可能であれば外注化のメリットは非常に大きくなります。
②受発注・カスタマーサポート対応
注文受付から配送手配、返品・交換対応、問い合わせ対応などのカスタマーサポート業務も外注可能です。
特に24時間体制での対応や繁忙期の問い合わせ対応には外部コールセンターやCS代行の利用が効果的です。
ただし、自社のブランドトーンや商品特性を理解した対応が求められるため、スクリプトの整備や定期的な教育・フィードバック体制の構築が成功のカギになります。
③広告運用(Google・SNS広告)
Google広告やSNS広告などの運用型広告は、専門知識が必要な分野のため、プロの広告代理店に外注することで効果を最大化できます。
広告運用の代行では、キーワード設定、予算配分、クリエイティブのテスト、配信結果の最適化など、データに基づいた施策を継続的に実施してくれるため、成果が出やすい傾向があります。
社内にリスティングやSNS広告のノウハウがない場合は、早期の外注化が推奨されます。
④クリエイティブ制作(画像・バナー)
商品画像やバナー広告、LPのビジュアル制作などのクリエイティブ業務も、専門のデザイナーや制作会社に外注可能です。
外部クリエイターはデザインのトレンドやマーケティング視点を持っており、成果につながるビジュアル制作が期待できます。
社内で撮影や編集のリソースが不足している場合は、撮影から編集まで一貫して対応する制作会社を選ぶことで、コンテンツ品質を安定させることができます。
⑤分析・レポーティング・改善提案
アクセス解析や広告効果測定、CVR改善などのデータ分析業務も、マーケティング専門の外注先に任せることができます。
GA4やShopify Analytics、広告ダッシュボードなどを用いたレポーティングに加え、課題の特定と改善施策の提案までを一貫して対応してくれる業者も増えています。
数字を読める人材が社内にいない場合や、運用の改善PDCAが回っていない場合には、外注のメリットが非常に大きい分野です。
EC運営代行会社の選び方
EC運営代行会社を利用することで、自社のリソースを最適化しながら売上アップを図ることが可能です。
しかし、依頼先を誤ると「費用が高いだけで効果が出ない」「連携がスムーズにいかない」といった失敗に陥るケースもあります。ここでは、失敗しないための代行会社の選び方を4つの視点でわかりやすく解説します。
▼EC運営代行会社の選び方
|
選び方①|得意領域(広告運用・制作など)を確認する
運営代行会社といっても、すべての業務を均等にカバーしているわけではありません。
広告運用に強い会社、クリエイティブ制作に特化している会社、物流やカスタマーサポートを得意とする会社など、それぞれの得意分野は異なります。
自社の課題に合った業務領域で強みを持つパートナーを選ぶことで、費用対効果の高い委託が実現できます。初回面談では「何ができるか」ではなく「何が得意か」を必ず確認しましょう。
選び方②|費用体系(固定・成果報酬)をチェックする
代行費用の体系も重要な比較ポイントです。月額固定費型は安定した支払いで予算が組みやすい一方、売上に連動しないため、成果が出なくてもコストが発生します。
一方、成果報酬型は初期費用が抑えられる反面、売上の一定割合を支払う必要があり、長期的には割高になる可能性もあります。
複数の業者の見積もりを比較し、自社のフェーズ(立ち上げ期/成長期)に合った課金モデルを選ぶことが重要です。
選び方③|過去実績・クライアント数を確認する
信頼できる代行会社かどうかを見極めるうえで、過去の実績や支援しているクライアント数は大きな判断材料になります。
とくに、自社と同業種・同規模の支援実績があるかどうかを確認することで、業界特有の課題への対応力や改善ノウハウを見極めやすくなります。
事例紹介やインタビュー記事、導入事例の有無をチェックするほか、できれば担当者に具体的な成果指標をヒアリングするのがおすすめです。
選び方④|サポート体制・連携方法を確認する
EC運営は日々状況が変化するため、スムーズな連携体制が整っているかどうかは非常に重要です。
定例ミーティングの頻度、専任担当者の有無、チャットツールでのやりとり可否など、実務的な連携フローを事前に確認しましょう。
また、トラブル発生時の対応スピードや、改善提案が定期的にあるかといった運用面の質も、長期的な成果に大きく影響します。契約前に試験的なプロジェクトから始めるのも有効です。
まとめ
EC運営を外注するか内製で行うかは、企業の成長段階や社内リソース、予算、目指す成果によって最適解が異なります。
外注は専門性とスピードを得られる反面、コストや連携の課題もあります。
一方で、内製は自由度やノウハウ蓄積の面で優れるものの、人手不足や属人化のリスクがつきものです。
まずは自社の現状と課題を明確にし、外注すべき業務と内製すべき業務を切り分けることが、安定的かつ成長可能なEC運営体制を構築する第一歩となります。
idiomは、10年以上にわたってECビジネスを支援し、これまでに100社以上との取引実績を持っています。
立ち上げから運用改善までを一貫して伴走し、多くの企業の成長を後押ししてきました。
さらに、運営継続率は95%と非常に高く、成果と信頼の両面で実績があります。
初期費用を抑えられる成果報酬型のプランもご用意しており、ECをこれから始めたい企業様でも安心してスタートいただけます。
▼▼▼まずはお気軽にご相談ください。▼▼▼
ECサイト運営代行のご相談はidiomへ