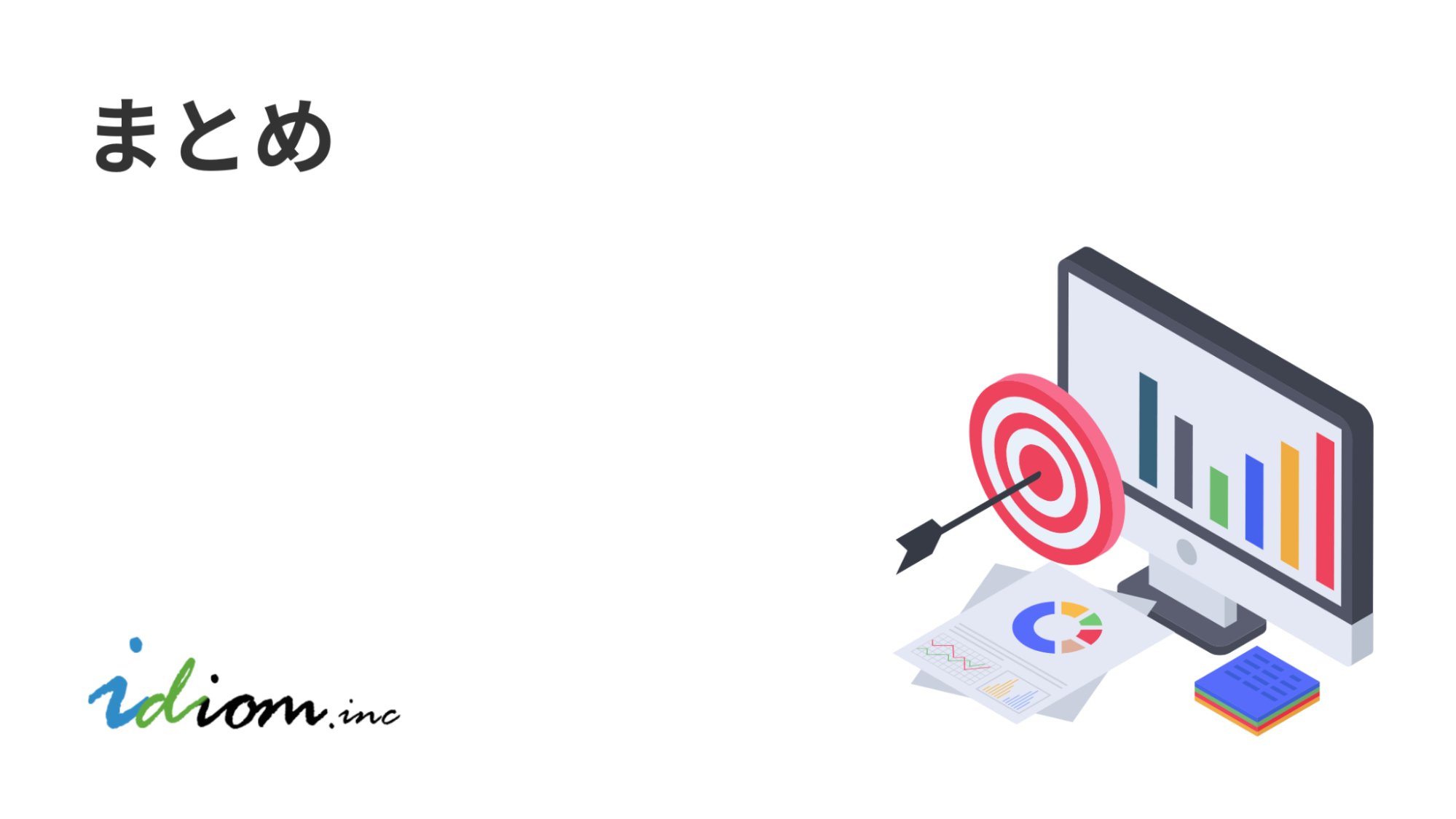化粧品業界で自社ブランドを広めたいなら「D2Cモデル」が効果的です。D2Cとは、商品を自社から直接お客様に届ける販売方法を指します。
中間業者をはさまず、自社からお客様に直接商品を届けるため、コストを抑えてファンを増やせるのが魅力です。
本記事では、D2Cが化粧品ビジネスに適している理由と、実際に成果をあげたブランド8選を紹介します。
この記事を読むことで、D2Cモデルで化粧品ブランドを成功に導く具体的な方法が見えてきます。
▼この記事でわかる内容
|
idiomは、長年に渡りECサイト構築・運用を支援し、これまでに120社以上との取引実績を持っています。
ECサイトの立ち上げから運用改善までを一貫して伴走し、多くの企業の成長を後押ししてきました。
さらに、運営継続率は95%と非常に高く、成果と信頼の両面で実績があります。
初期費用を抑えられる成果報酬型のプランもご用意しており、ECサイト構築を委託したい企業様でも安心してスタートいただけます。
▼▼▼まずはお気軽にご相談ください。▼▼▼
ECサイト構築のご相談はidiomへ
D2Cモデルが化粧品に向いている3つの理由
製造から販売までを一貫して行うD2Cは、顧客ニーズに即応しやすく、ブランド独自の世界観を届けるのに最適な手法です。以下では、化粧品とD2Cの相性が良い理由を3つに分けて解説します。
▼D2Cモデルが化粧品に向いている3つの理由
|
理由①|コスト構造が合っている
D2Cモデルでは、メーカーが直接消費者に商品を届けるため、従来の流通構造に必要だった中間マージンが発生しません。卸を介さないことにより、商品価格を抑えつつ、品質や製品設計にコストをかける余地が生まれます。
たとえば、リピーターを獲得するためにサンプルを無料で同梱したり、オリジナルボックスを採用するなど、ブランド価値の向上にもコストを充てやすくなります。
小資本でスタートしたい企業や、高付加価値型のブランド設計を目指す事業者にとっても、有効なビジネスモデルといえるでしょう。
理由②|個人ニーズに応える設計がしやすい
D2C化粧品の大きな強みは、ターゲットの悩みに寄り添った商品設計が可能な点です。肌質や年齢、季節の変化、ライフスタイルなど、消費者ごとの多様なニーズに対応できます。
従来の大量流通モデルでは、企画から発売までに半年以上を要することもあり、時代や市場ニーズに即応するのが難しいという課題がありました。
一方でD2Cモデルでは、ユーザーからのフィードバックを受けながら、短いサイクルで製品改良や新商品開発が可能です。
D2Cでは、ニッチな悩みに応じた商品展開をスピーディかつ低リスクで実現できます。D2C化粧品は、画一的な大量生産から脱却し、パーソナルケアの時代に応える存在として注目を集めています。
理由③|SNS発信と相性が良い
D2C化粧品の強みのひとつは、SNSを活用した情報拡散との相性の良さです。
化粧品は「テクスチャーの美しさ」「使用前後の違い」など、視覚的に訴求できる要素が多く、SNS向きの商材といえます。
購入者からの口コミ投稿やレビューも重要なポイントです。実際に使用したユーザーのリアルな声は、新規顧客にとって大きな購入判断材料になります。UGC(ユーザー生成コンテンツ)としてブランドの信頼性を高める要素にもなります。
D2C化粧品の成功事例8選
▼D2C化粧品の成功事例8選
|
事例①|ORBIS(オルビス)
引用元:ORBIS
ORBIS(オルビス)は、1987年に通信販売からスタートした日本発の化粧品ブランドです。創業当初から、販売店を介さずに顧客へ直接商品を届けるD2Cモデルを採用しています。
ターゲットは、30〜40代の敏感肌・年齢肌に悩む層です。オンラインカウンセリングやパーソナル診断など、顧客ごとの悩みに応じた提案に強みがあります。
定期購入サービスに力を入れており、2025年3月には通販売上の20%以上を定期購入が占めるまでに成長しています。
SNSでは機能性や世界観をビジュアルで伝え、共感を呼ぶ投稿を重視するなど、デジタルと連動したD2C戦略が特徴です。
事例②|Glossier(グロッシアー)
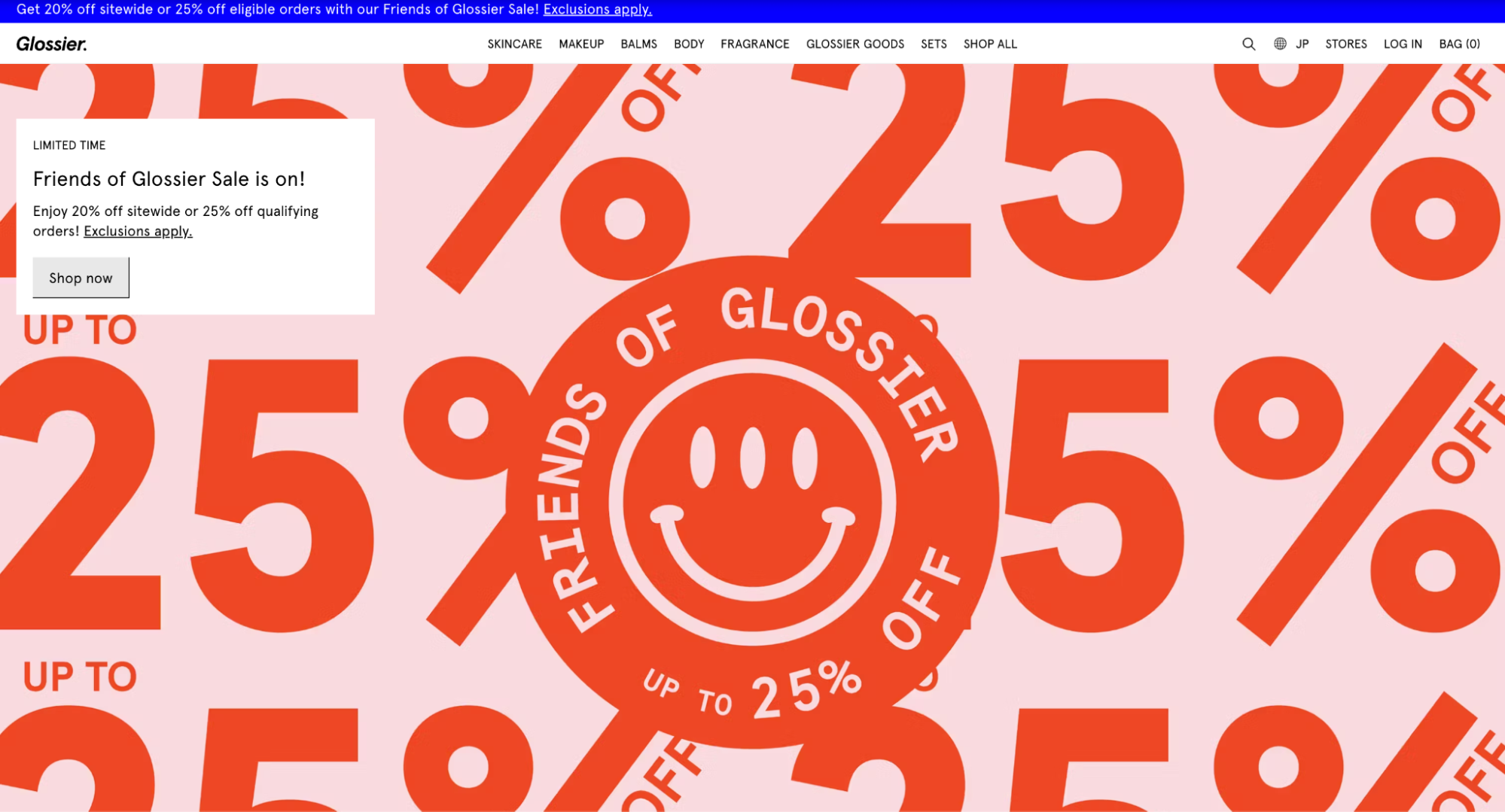 引用元:Glossier
引用元:Glossier
Glossierは、米ニューヨーク発のD2Cブランドです。「Skin First, Makeup Second」をコンセプトに、素肌の美しさを引き出すスキンケアと、ナチュラルなメイクアップ商品を展開しています。
ターゲットは20〜30代で、SNSに親しみがあり、美容感度の高い層が中心です。
ユーザーが投稿する写真やレビューを活用することで、ブランドの世界観と一体化したコミュニティを形成しています。商品開発にも顧客の声を取り入れており、UGCを軸にした共創型のマーケティングが特徴です。
販売はオンラインが中心で、ポップアップストアなど体験を重視した施策も組み合わせながら、ブランドのファン層を広げています。
事例③|BOTANIST(ボタニスト)
 引用元:BOTANIST
引用元:BOTANIST
BOTANISTは、植物由来の成分にこだわったシャンプーやボディケア製品を展開するボタニカルライフスタイルブランドです。
無駄をそぎ落としたシンプルなボトルデザインと、やさしい植物の香りが調和した使い心地で、性別や世代を問わず幅広く支持を集めています。
SNSを通じたブランド発信に加え、期間限定のポップアップストアや体験型イベントを実施するなど、五感に訴えるマーケティングが特徴です。
2023年にはシリーズ累計1.6億本を突破し、1000円以上のプレミアム価格帯市場において確かな地位を築いています。
事例④|ドモホルンリンクル
 引用元:ドモホルンリンクル
引用元:ドモホルンリンクル
ドモホルンリンクルは、再春館製薬所が手がける年齢肌専門のスキンケアブランドです。加齢による肌の悩みに真正面から向き合い、年齢に応じた肌の変化を受け入れながら、肌本来の力を引き出すケアを提案しています。
独自に開発した成分と処方は、長年の研究成果に基づいており、東洋医学の知見を取り入れた製品設計が特徴です。漢方の考え方をベースに、体と肌のつながりを重視したアプローチを採用しています。
初回購入時から丁寧なカウンセリングを提供し、一人ひとりに寄り添う姿勢を大切にしています。その結果、継続利用者が非常に多く、定期購入者のうちおよそ94%がリピートしており、その半数近くは10年以上継続しているそうです。
EC経由の接点が最も多く、新規顧客の約9割がオンライン経由である点も特徴的です。
事例⑤|N Organic(エヌオーガニック)
 引用元:N Organic
引用元:N Organic
N Organicは、植物由来の成分にこだわった国産オーガニックコスメブランドです。精油の香りと肌なじみの良さが特徴で、肌と心の両方に寄り添うスキンケアを提案しています。
ターゲットは30〜40代の女性で、ナチュラル志向や丁寧な暮らしを大切にする層に支持されています。
販売チャネルはECが中心です。まずトライアルキットを通じて使用感を試してもらい、その後は定期購入につなげる導線が構築されています。
近年は直営店も展開し、肌診断を取り入れた接客を行っています。
SNS広告やオンラインカウンセリングと連携させながら、顧客一人ひとりに向き合う姿勢を大切にしています。
事例⑥|SHIRO(シロ)
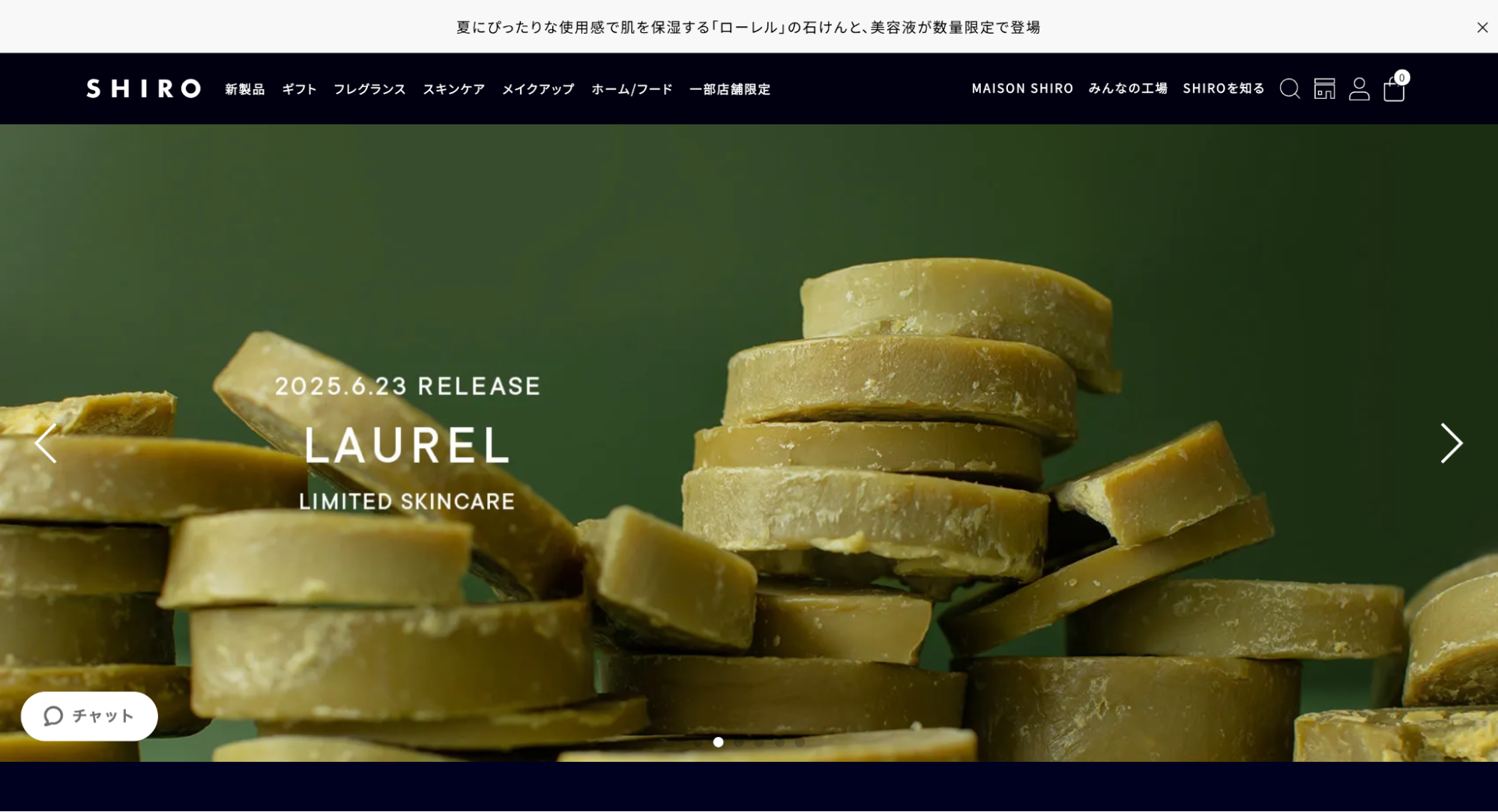 引用元:SHIRO
引用元:SHIRO
SHIROは、国内発の自然派ビューティーブランドです。北海道産のがごめ昆布、酒かす、ゆずなどをふんだんに使い、肌へのやさしさと機能性を両立する処方に強みがあります。
ターゲットは30〜50代の自然志向の男女で、エシカルな素材選びや環境配慮に敏感な人々に支持されています。販売は全国の直営店やECが中心です。
SNSでは、素材のこだわりや製品づくりの背景を丁寧に発信し、ブランドの世界観や透明性を伝えることでファンを獲得しています。
肌悩みに合わせた商品提案を通じてオンラインでも満足度の高い購買体験を提供し、国内外でファンを拡大し続けている点も特徴です。
事例⑦|スプレーゼ
 引用元:スプレーゼ
引用元:スプレーゼ
スプレーゼは、化粧品研究系YouTuberのすみしょう氏が立ち上げたスキンケアブランドです。大手化学メーカーでの研究経験を活かし、成分の安全性や効果にこだわったシンプルな処方設計が特徴です。
ターゲットは20〜40代の敏感肌・乾燥肌に悩む女性で、科学的根拠に基づいた丁寧な商品づくりに共感が集まっています。
YouTubeやInstagramでは、商品の開発背景や成分の解説をわかりやすく発信し、ブランドへの信頼を高めています。
販売は自社ECや楽天などのオンラインチャネルを中心に展開しており、フォロワーの声を商品設計に反映するなど、ユーザー参加型の開発スタイルも強みです。
SNSから購入への流れが自然につながる、デジタル起点のD2Cモデルを確立しています。
事例⑧|DUO(デュオ)
 引用元:DUO
引用元:DUO
DUOは、プレミアアンチエイジングが手がけるスキンケアブランドで、クレンジングバーム市場のパイオニア的存在です。
看板商品の「ザ・クレンジングバーム」は2025年1月末に累計出荷個数5,500万個を突破し、毛穴ケアに悩む30〜50代の女性を中心に高い支持を集めています。
販売戦略は、ECと定期購入を軸にしながら、テレビCMやSNSを活用するハイブリッド型です。有名タレントを起用した広告で認知を拡大しつつ、口コミやレビューによる自然な拡散も促しています。
SEO × CRMで差をつける化粧品のD2C施策2選
 化粧品D2Cブランドが継続的に顧客を獲得し、LTV(顧客生涯価値)を最大化するには、単なる商品訴求だけでは不十分です。競合との差別化を図るためには、SEOによる安定的な集客と、CRMによる関係性の強化が欠かせません。
化粧品D2Cブランドが継続的に顧客を獲得し、LTV(顧客生涯価値)を最大化するには、単なる商品訴求だけでは不十分です。競合との差別化を図るためには、SEOによる安定的な集客と、CRMによる関係性の強化が欠かせません。
ここでは、SEOとCRMの2つの施策について具体的に解説します。
▼SEO × CRMで差をつける化粧品のD2C施策2選
|
施策①|SEO
D2C化粧品ブランドにとってSEOは、広告費を抑えながら見込み顧客との接点を増やせる集客手段です。検索エンジンを通じて、悩みを持つユーザーに情報を届けることで、自然なかたちで認知・興味・購買へとつなげることが可能になります。
なかでも、「D2C 化粧品 メリット」「30代 敏感肌 スキンケア」などの具体的なキーワードを軸にした情報提供は、検索意図に応じた的確なコンテンツ設計につながります。
たとえば、コスメレビュー記事では「実際に使ってどうだったか」といった使用感や肌との相性が伝わり、共感を呼びやすくなります。HOW TO型の記事では、「正しいクレンジングバームの使い方」「成分から選ぶスキンケアの選び方」など実用的なテーマが効果的です。
また、「D2Cとは何か」「定期購入はお得なのか」といったQ&A型のコンテンツも、初心者層の疑問解消につながります。
SEOではE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)に基づく構成が重要です。医師や研究者の監修付き記事、第三者レビューの引用、実際のユーザーの声を掲載することで、情報の信頼性が高まり、検索上位にも反映されやすくなります。
施策②|CRM
化粧品D2CにおけるCRM(顧客関係管理)は、購入後の満足度や継続率を左右する重要な要素です。商品単体での売上にとどまらず、リピート購入やブランドロイヤルティの形成を目指すためには、CRM施策を丁寧に設計する必要があります。
代表的な手法のひとつが、メールマーケティングやLINE配信による「ユーザー育成」です。購入直後に感謝のメッセージを送るだけでなく、使用方法や成分の解説、季節ごとのスキンケア提案を自動配信することで、商品への理解と信頼が深まります。
ステップメールやステップLINEを活用すれば、ユーザーの行動履歴に合わせたパーソナライズ配信も可能です。
誕生日クーポンやポイント還元、初回購入者向けのお得な定期コース案内なども、LTV(顧客生涯価値)を高める施策として有効です。特に化粧品は「使い続けて効果を実感する」性質が強いため、一定期間の継続使用を促すインセンティブが重要となります。
D2C化粧品を成功させる6つのポイント
 D2Cモデルで化粧品ブランドを成功させるには、商品力だけでなく、ブランド全体の伝え方や顧客との関係づくりが重要です。ここでは、D2C化粧品ブランドが成果を上げるために押さえておきたい6つのポイントを紹介します。
D2Cモデルで化粧品ブランドを成功させるには、商品力だけでなく、ブランド全体の伝え方や顧客との関係づくりが重要です。ここでは、D2C化粧品ブランドが成果を上げるために押さえておきたい6つのポイントを紹介します。
▼D2C化粧品を成功させる6つのポイント
|
ポイント①|悩み明確化とUSP訴求
D2C化粧品ブランドが成果を上げるには、まず「誰の、どんな悩みを解決するか」を明確にする必要があります。
肌の乾燥・敏感・毛穴・シミなど、化粧品がアプローチする悩みは多様です。商品設計を行う段階で「どの悩み」に「どんな根拠」で対応するのかを定義し、情報発信やパッケージ、LPに一貫性を持たせましょう。
また、USPの設計も重要なポイントです。USPとは、自社の商品やブランドだけが提供できる独自の価値や強みを指します。
たとえば「ヒト型セラミドを高濃度で配合」「医学誌に掲載された処方を採用」「肌診断付きの定期購入サービス」など、具体的かつ信頼できる訴求があると差別化につながります。
誰の悩みをどう解決するか、なぜ自社が最適なのかを明確に伝えることで、D2Cブランドの魅力はより鮮明になります。
ポイント②|SNS/UGCの活用
D2C化粧品ブランドにとって、SNSは商品の魅力を伝えるだけでなく、ブランドの世界観や価値観を発信する大切な場です。
特にInstagramやYouTube、TikTokなどのプラットフォームは、視覚的・感覚的に訴求しやすい化粧品と非常に相性が良く、活用次第で大きな集客効果と信頼獲得につながります。
SNS施策で重要なのは、「広告的」な投稿だけでなく、ユーザーの投稿=UGCを活用することです。実際に商品を使っている人の感想やビフォーアフター画像、開封動画、ルーティン紹介などは、企業発信よりもリアリティと説得力があります.
UGCが拡散されることで、商品への関心が自然と高まり、購入意欲にも直結します。
ポイント③|ファンコミュニティ作り
D2C化粧品ブランドが長期的に成長するためには、単発の購買ではなく、ブランドへの継続的な共感と信頼を築くことが欠かせません。
そのために有効なのが「ファンコミュニティ」の形成です。単なるフォロワー数の拡大ではなく、ブランドの価値に共鳴し、能動的に関わってくれる“仲間”の存在がブランドの継続性を支えます。
最近では、LINEオープンチャットや招待制のオンラインサロン、会員限定のイベントなど、よりクローズドで深いコミュニケーションを育む場を設けるブランドも増えています。
リアルイベントでは、製品の体験会や開発者との座談会を通じて、ブランドとの一体感を高めることが可能です。
ファンコミュニティを持つことの最大の利点は、単なる購入者ではなく、「応援者」が育つことにあります。UGCの投稿や口コミ拡散、商品開発協力など、ブランドの成長に自発的に貢献してくれる存在は、広告では得られない価値をもたらします。
ポイント④|LP/ランディング構成
D2C化粧品ブランドにとって、LPは商品との出会いの場となる大切な接点です。検索やSNS広告などを経由して訪問するユーザーに対し、ブランドの印象や商品理解を深めてもらう役割を担っています。
特にオンライン販売が中心となるD2Cモデルでは、LPの設計が購入の判断に大きく影響します。
商品の魅力だけでなく、ブランドが大切にしている考え方や世界観がさりげなく伝わる構成にすることで、単なる商品の紹介を超えて、継続的な関係づくりにもつながります。
ポイント⑤|薬機法・表示規制への配慮
D2C化粧品ブランドを運営する上で欠かせないのが、薬機法(旧・薬事法)をはじめとする表示規制への適切な対応です。
インターネットを通じて消費者と直接つながるD2Cでは、広告やLP、SNS投稿、商品パッケージなど、さまざまな場面で商品情報を伝える必要があります。そのため、どこでどのような表現を使うかには十分な注意が求められます。
薬機法に準拠したコピーライティングや、専門家による監修体制を整えておくことで、社内でも安心して表現できる環境が生まれます。特にLPや広告バナーは外部ライターや広告代理店に委託されることも多いため、共通のチェック基準や教育も大切です。
ポイント⑥|定期購入メニュー設計
D2C化粧品ブランドのビジネスモデルにおいて、定期購入は売上の安定化と顧客との長期的な関係構築に貢献する重要な仕組みです。
特にスキンケア商品は、一定期間継続して使用することで効果を実感しやすいため、定期的に届けるサービスとの相性が良いとされています。
定期購入メニューを設計する際に重要なのは、無理なく継続できる仕組みを用意することです。たとえば、商品使用ペースに応じた配送間隔の選択や、次回のスキップ・休止が簡単にできる設計は、心理的なハードルを下げます。
商品同梱のチラシやLINEでのフォロー、購入サイクルに合わせたアフターフォローなども効果的です。
定期購入は「売る仕組み」ではなく「続けやすくする体験設計」であることを意識することで、解約率の低下とファン化が同時に進みます。
idiomは、長年に渡りECサイト構築・運用を支援し、これまでに120社以上との取引実績を持っています。
ECサイトの立ち上げから運用改善までを一貫して伴走し、多くの企業の成長を後押ししてきました。
さらに、運営継続率は95%と非常に高く、成果と信頼の両面で実績があります。
初期費用を抑えられる成果報酬型のプランもご用意しており、ECサイト構築を委託したい企業様でも安心してスタートいただけます。
▼▼▼まずはお気軽にご相談ください。▼▼▼
ECサイト構築のご相談はidiomへ
まとめ:D2C化粧品で成功するために
本記事では、D2Cモデルが化粧品と相性の良い理由から、成功事例、具体的な施策、押さえておくべきポイントまでを体系的に解説しました。
化粧品は個人の悩みに深く関わる商材であり、SNSやECを通じてユーザーと直接つながれるD2Cモデルと相性が良いといえます。
肌質やライフスタイルに合わせた提案、成分のストーリー、継続利用による効果実感などを、ブランドが直接伝えられることはD2Cならではの強みです。ユーザーとの信頼関係を築きやすく、継続利用やファンの獲得にもつながりやすくなります。
D2C化粧品ブランドを成功させるために、顧客の悩みに寄り添いながら、魅力あるブランド体験を一貫して提供し続けましょう。